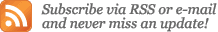今作っている船井総研の小山会長との対談の一部を先行掲載します。テーマは「絆」です。
■小山 イノベーションの芽は既にあるものの中にあります。マーケットの動きには必ず兆しがありますから、その兆しを察知して既にあるものを革新する、これがイノベーションの基本でしょう。イノベーションにはこれまでの世の中に存在しないものを生み出す、という事もありますが、むしろこれは中々成功にはつながらないように思います。
■司会 最先端を行きすぎると案外成功しないというのも同じですね。
■小山 例を上げれば「AKB48」でしょう。先行者は「おニャン子クラブ」であり、「モーニング娘。」ですが、この先行事例を秋葉原を拠点とした「手の届くアイドル」路線でイノベートしました。握手会をファンとの重要接点に置いたこともこの路線の延長です。これが革新的で、おタクマーケットの熱狂的支持を生みました。これにより、日陰の存在であった「オタク」がマーケットの主役になりました。おタク市場の潜在バイイングパワーを「AKB48」は最大に引き出したのです。「AKB48」の登場は金太郎飴マーケティングの終焉と、「日本人1億総オタク」時代への突入を象徴しています。
■横井 今のお話を別の角度でいえば、やはりアナログが大事だという事です。リアルであるという事ですね。「手の届く現実」という事です。今年のキーワードの「絆」もリアルな結びつきを前提にしています。まさしくAKB48 の「握手会」はその象徴です。 先日セブンイレブンの話を聞いたのですが、電子マネーの「nanaco」の顧客情報を分析してわかったことがあるというのです。セブンイレブンのそれまでの感触では近隣の固定客は1000人はいると見込んでいたのですが、「nanaco」の分析で半分程度しかいないことが判ったというんですね。そこからがすごいと思うのですが、普通ならそれでは新規の固定客を増やそう、とするのが当たり前ですが、セブンイレブンは現在の固定客との「絆」を深める方針を取った。それをまずは顔と名前を覚えるところから始める、というのです。更に固定客の好む商品の品ぞろえを強化するというのです。この話を聞いて感心しました。今最も大事なことは顧客を増やす事より、既存顧客との絆を深める事だからです。
■小山 なるほど。新規顧客の獲得のトータルコストを考えたら、既にファンでいてくれている固定客の来店頻度を上げる事の方が投資回収面でも効果的ですからね。
■横井 この話を聞いて改めて思いましたが、間違いなく、これからのビジネスで一番大事なことは顧客との結びつき、英語でいえば「Customer Engagement」です。これを強め、深める事だという事です。「結びつき」とは損得や打算を超えた情緒的な感情に支えられています。セブンイレブンがやろうとしている固定客の顔と名前を覚えるとは正しく、顧客の情緒に訴えて絆を深めるという事です。顧客満足で評判のリッツカールトンの強みもここにあります。リッツカールトンと聞くと別世界に思えても、コンビニだって取り組んでいるのです。あらゆるビジネスでこれこそ直ちに取り組むべきことなのです。そういった顧客との結びつきを真摯に重視する企業姿勢の延長でしか、最近はやりのSNSなどを使ったデジタルなマーケティングも成功しません。
■司会 よく判ります。顧客との結びつきを深め、強めることの重要性は言うまでもないですが、そこで留意する点にはどういう事がありますか。
■横井 二つあるでしょうね。まずは自社がやっている事業は、単なる損得勘定ではなく、自社の商品やサービスを通じた「良い世の中づくり」いわば「社会貢献なのだ」という事をしっかり自己定義できている、という事です。顧客のロイヤルティーが高い、顧客との結びつきが強い企業に共通する事はここです。 スターバックスのハワードシュルツはこのことを「ロマンチックと効率の両立」と言っています。ここで効率と言うのは「損得勘定はしっかりする計算する」という事ですが、それはロマンチック、すなわちスターバックスが重視する人間重視の経営姿勢を維持、強化する事とのバランスにおいて為されなければならない、という事です。顧客との結びつきは言うまでもなく効率の問題ではなく、“ロマンチック”な問題なのです。
■司会 なるほど、もう一つは何ですか?
■横井 二つ目は従業員との結びつきです。結局顧客との結びつきの最前線は現場の顧客接点なのです。そこで実際に顧客にサービスする第一線の従業員です。だから顧客との結びつきを強めようとする、すなわちお客様にわが社を「好きになって頂く」、もっと言えば「愛していただく」には、従業員が会社の事を「大好き」で、「愛している」ことが不可欠なのです。 だから顧客との絆(Customer Engagement)を深めたければ、先ず従業員との絆( Employee Engagement)を強く深くすることが必要です。これを言うと給料や福利厚生の事を言っていると早合点する人がいますが、従業員も顧客同様に損得勘定だけで働いているのではありません。ここでも“ロマンチック”が大事なのです。ドライな割り切りを前提にした成果主義がたいてい失敗する理由は、ここにあります。
■司会 そういえば、会長が最近協商されていることにマズローの第6段階目の欲求の話があります。横井さんが今回のセミナーで取り上げるテーマにもそれに近いお話があるようですね。マズローの自己実現欲求も単に金銭的な成功を指しているのではなく、更にその先に人生の究極の欲求があるという事ですが・・・。
■小山 マズローの生存欲求、安全欲求、社会的欲求、自我の欲求、自己実現欲求の5段階欲求には最後の6段階目があるのですね。それは「他者への奉仕、利他」という事なんですが、「人のためになることをしたい」という事が人間の求める最終到達系の欲求なんです。だから今の話も良く理解できます。
■横井 マズローの欲求説はモチベーション理論でもあるのですが、最も人間をモチベート(動機付ける)するのは最終的には「世のため、人のためお役にたつ」という事なんですね。私もようやく其れが判る様になりました(笑)。私はどちらかというと5段階目の「自己実現欲求」を満たすための条件が「他者への奉仕」だと思っていましたが、ズバリそれが6番目だったんですね。
■司会 従業員のやる気を喚起する、という事も今回のセミナーのテーマですが、これは企業のイノベーション能力を高めるためにも大事なことです。その為には、マズロー流にいえば、世間並みの働く環境、すなわち生存欲求、安全欲求、更に社会的欲求を満たす条件を整えて、その上で高位の自我の欲求、自己実現欲求、更に利他の欲求を満たす経営の目的、大義を打ち出す事が必要だ、いう事でしょうか。
■小山 そうです。それがこれからの経営で一番大事なことです。しかしその為にも、まずは即時業績向上法で、強みを見つけ、それを伸ばす、そして企業を元気にしてその上でしっかり抜本策を進める、こういったお手伝いを今年はやりたいものです。それが船井総合研究所、我々の社会貢献です。
■司会 そのお手伝いの皮切りとしてお二人のセミナーを開催したいと思っています。ぜひ多くの方に参加いただいて、ツキと勢いを呼び込むきっかけにして頂きたいですね。その上で長期的な経営基盤の強化策をのヒントも掴んで頂きたいと思います。