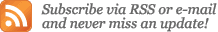昨日紹介したチャンネル桜の「大東亜戦争開戦70周年大討論会」の映像ですが、寝床で聞いていたので、ところどころ聞き漏れがあって、昨日仕事の合間の移動時間に改めて聞きました。 京大の藤井さんの「パールハーバーから終戦に至る間、日米は軍事的に戦ったが、実際は1853年のペリー来航(黒船)以来、現在も文化的、経済的戦いが続いているのだ。その象徴がTPPだ。」という話には頷けました。
それではその戦いの本質とは何かですが、それも西部先生ほかの皆さんがしっかり定義してくれています。それはアメリカに象徴される近代合理主義と日本的なるものと戦いである。という事です。 そして近代合理主義の基本的仕組みでる資本主義(グローバリズム)との戦いであるとも定義しています。 更にその資本主義、そして近代合理主義が行き詰まった現在、反グローバリズムの、また反個人主義の実在する理念を提示できるのは日本だけである、という事が論じられています。
西尾幹二さんがその象徴として、どの国の人が一番親切か、というテレビ番組の内容を紹介しています。沢山のみかんを誤って落としたとき、周りの人の何人が手伝って拾ってくれるかという実験を各国でしたそうです。 一番少ないのは中国で20人中1人、アメリカは7人、イタリアは多くて15人、日本は20人だったそうです。
また荒谷さんがフランスでの体験で震災後の日本人のいたわり合い助け合う姿を見て、真剣に「なぜそういうことができるのか」を政府関係者をはじめみな真剣に知りたがっていた、という事を話されていました。 そういった姿が反グローバリズム、反個人主義の理念の行動としての「現れ」なわけですが、そういったいわば日本的な精神性を最もわかりやすく提示してくれるのは新渡戸稲造の武士道でしょう。
私がこの本を読んだのは数年間です。ウラジヲストックからハバロフスクへのシベリア鉄道の眠れない車中で読みましたので、ひときわ印象深いです。 その時初めて知りましたが、新渡戸はこの本を英語で書きました。また新渡戸はキリスト教の熱心な信者で、第二大戦中は非戦論を唱ええて、総長を務めた東大を追われています。 武士道と聞くと好戦的で、封建的に思われがちですが、新渡戸自身がそうであるように、この本を読むと「武士道精神」が普遍的なもので、まさに先の「反グローバリズム、反近代合理主義の実在理念を提示できるのは日本である」という論点がよく理解できると思います。 日本人なら自らのアイデンティティの確認のためにも一度は読んでおきたい本です。

武士道